
今回は俵万智さんの随筆文『生きる言葉』が出題されました。
俵万智さんは、歌人・木下龍也さんとその短歌を学習したAI(通称「木下さんAI」)によるイベントを通して、「AI短歌」と「人間の短歌」を比較し、それぞれが持つ力と限界について深く考察しています。小学生に身近な内容ではないですが、筆者の主張を読み取ることができたでしょうか。
- 文章の概要
- 重要問題解説 問1‐2・問5・問6・問7・問9
- (問1‐2)記述問題 「みんなとは違う港」で「帆をたたむ」とはどういうことを表していますか。30字以内で具体的に答えなさい。
- (問5)選択問題 「やるじゃないかAI」とありますが、AIが作った「『自由』と呼ぶのは~」という歌を、筆者がこのように評価したのはなぜですか。
- (問6)選択問題 AIがつくった短歌について、筆者の思いは、=線Ⅰ「こんなにグッときてしまう自分が、ちょっと怖かった」から、=線Ⅱ「その感動は、作者がAIだからといって無くなるものではないと感じる」へと変化しています。このことについて説明した次の文の[A]~[C]にあてはまるものを後から一つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
- (問7)選択問題 ー線⑦「一部の選考委員は批判的な発言をした」とありますが、この場合の「批判的な発言」とはどのようなものだと考えられますか。
- (問9)記述問題 ー線⑧「恩返しをする鶴は、自分の羽を織りこむからこそ、輝く布を織ることができる」とありますが、これは木下さんが依頼者のリクエストに応えて短歌を詠む時の姿勢や作業の方針を表しています。木下さんはどのようなことに注意しながら、歌を詠んでいるのでしょうか。50字以内で、具体的に答えなさい。
- 四谷大塚「第2回合不合判定テスト」 随筆文まとめ
文章の概要
要約
イベントでは、読者の依頼文に応じた短歌を人間とAIがそれぞれ作成。その中で、AIの短歌が予想以上に人の心を打つ表現を持ち、感動を引き起こす一方で、AIには「意図」や「心」がないことにも気づかされます。
人間の歌人である木下さんは、依頼に自分の「心のフック(引っかかり)」を見出し、そこから詩を生み出していました。このプロセスが、AIにはない「詩に命を吹き込む力」であると俵さんは述べています。
筆者の主張・意見
- 短歌は「意味」だけでなく、「心」が込められることで感動が生まれる。
- AIの短歌にも人を動かす表現があるが、それは読み手の解釈が加わって初めて成立する。
- 創作において「自分の心を織り込む」ことが、AIには真似できない人間の営みであり、詩の本質だと考えられる。
重要語句・表現
- 心のフック:創作のきっかけや動機となる、心に引っかかる出来事や感情。
- ケージ:檻、閉じ込められた空間の比喩
- 恩返し鶴の羽:自分の心の羽を織り込むような姿勢があるという比喩。
- 培養される:育てられ、発展する
- 虚構:事実でない創作された内容
- シチュエーション:状況
- リスペクト:尊敬
重要問題解説 問1‐2・問5・問6・問7・問9
今回は、比喩表現を一般的な表現に言い換える記述問題(問1‐2・問9)、筆者のAI短歌に関する考えを問われた選択問題(問5・問6)、「短歌の選考員の批判的な発言」の内容を問われた選択問題(問7)を解説します。
(問1‐2)記述問題 「みんなとは違う港」で「帆をたたむ」とはどういうことを表していますか。30字以内で具体的に答えなさい。
■(問われていること)を確認する
この問題では、「どういうことを表していますか」と問われています。「どういうこと」と問われている問題は言い換える問題で、短歌の中の比喩表現「みんなとは違う港」「帆をたたむ」が何を意味しているのかを、説明することが求められています。
さらに、「具体的に答えなさい」と書いてあることから、具体的に言い換えることを意識して記述を完成させましょう。
■比喩表現を言い換える
この短歌に出てくる「みんなとは違う港」「帆をたたむ」は、それぞれ人生や生き方を、船旅にたとえた比喩です。
〈「みんなと違う港」とは〉
港とは、船が航海を終えてたどり着く場所です。つまりここでは、人生の選択の行き先(生き方の落ち着く場所)を意味しています。
つまり、「みんなとは違う港」とは、「多くの人が選ぶ人生の形ではなく、自分にとってふさわしい生き方」を表しています。
〈「帆をたたむ」とは〉
船が港に着いたとき、風を受けて進むための帆をたたむことです。帆をたたむということは、「目的地に到着し旅を終えたこと」を意味しています。
つまり「みんなと違う場所で帆をたたむ」という表現は、「多くの人が選ぶ人生の形ではなく、自分なりの目的地を見つけて、そこに落ち着いた」ということなのです。
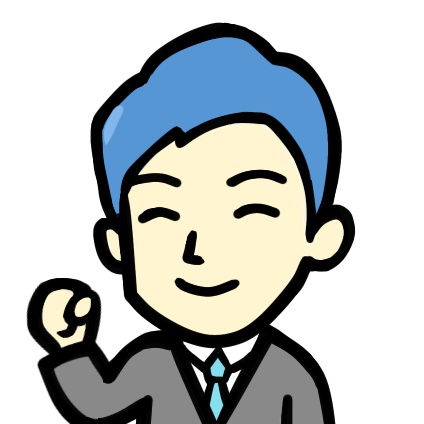
この比喩が理解できなかったお子さんが多かったのではないでしょうか。丁寧に解説してあげましょう。
■比喩を具体的にして、記述を完成させる
続いて、比喩が表すものを具体的にして、記述を完成させましょう。
「多くの人が選ぶ人生ではない自分なりの人生」とは、具体的にどのようなじんせいなのでしょうか。これは、結婚しないこと・子どもを持たないことを選んだ依頼者の人生であることが読み取れます。
そこで、これらを30字以内で簡潔にまとめていきましょう。
[模範解答]
→ 結婚しない、子どもも産まないという生き方を選ぶこと。
このように、比喩を具体的な人生の選択と結びつけて考えることで、的確な記述が可能になります。
(問5)選択問題 「やるじゃないかAI」とありますが、AIが作った「『自由』と呼ぶのは~」という歌を、筆者がこのように評価したのはなぜですか。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「筆者がこのように評価したのはなぜですか」という部分です。「やるじゃないかAI」という筆者の評価の理由を問われています。つまり、「なぜ筆者はAIの短歌に感嘆したのか」を、本文の描写や心情の変化から読み取る力が問われています。
■本文から筆者の考えを読みとる
選択問題のコツは、選択肢を見る前に自分で答えを考えることです。筆者の考えを読み取りましょう。
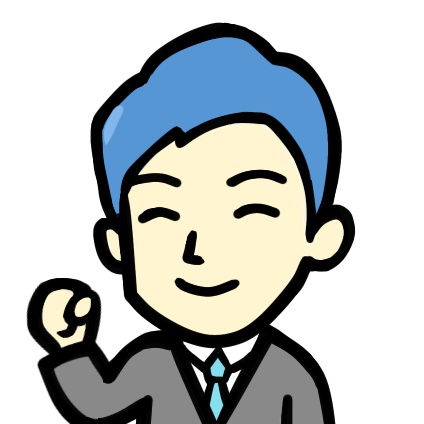
まぎらわしい選択肢に惑わされないため、まずは自分で答えを考える習慣をつけましょう。
AIの短歌「『自由』と呼ぶのはきみがきみのためにつくる小さなケージだけど」は、一読すると冷たく感じられます。筆者も「喧嘩売っとんのか」と感じたとあります。しかし、繰り返し読むうちに、「自由」の定義を狭めてしまう危うさや、別の視点の大切さに気づき、最終的には「悪くない」と評価し、「やるじゃないかAI」と感嘆するのです。
つまり、最初は否定的に感じた歌が、視点を変えることで、前向きで深い意味を持つ作品だとわかり、感動したという流れが読み取れます。
■選択肢の間違いを見つけて正答を導く
選択肢は、間違っているところを見つける意識で読んでいきます。テストの振り返りでどこが間違っているかお子さんに説明させることで、読解力は高まります。
✕イの誤り
「外に出る勇気を持てなかった依頼者に寄り添う優しさが、さりげなく込められていた」
→ この選択肢は「優しさ」をポイントにしていますが、筆者はこの短歌を「優しくはない」と最初に受け取っています。最終的に評価を変えたのは、視点の転換による意味の深さであり、「寄り添いの優しさ」ではありません。
✕ウの誤り
「人と同じものを持つことで感じる幸せを軽んじている」
→ そのような内容は本文にはありません。この選択肢は「花の歌」と混同しており、ケージの歌の鑑賞としては不適切です。
✕エの誤り
「不幸な我が身を嘆くなという叱咤激励」
→ AIの短歌に「叱咤激励」の意図を見出すのは読みすぎです。筆者は、「定義によって自由を狭める危うさ」という知的なメッセージに気づいたのであって、感情的な励ましとは違います。
つまり、本文に書かれている「定義が自由を狭めてしまうという気づき」と、「最初は厳しく見えたが、読み直して感動した」という筆者の変化を正しくとらえている ア が正答であると判断できます。
[正答] ア
→ 救いを求める依頼人の思いを踏みにじる非情な歌とも思えるが、少し視点を変えることで、心が救われる可能性があることを示した、前向きなメッセージとして受けとることもできる、奥の深い歌であることに気がつき、感嘆したから。
(問6)選択問題 AIがつくった短歌について、筆者の思いは、=線Ⅰ「こんなにグッときてしまう自分が、ちょっと怖かった」から、=線Ⅱ「その感動は、作者がAIだからといって無くなるものではないと感じる」へと変化しています。このことについて説明した次の文の[A]~[C]にあてはまるものを後から一つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
AIが作った短歌に対する筆者の気持ちの流れを読み取る問題です。
Ⅰでは、[A]。しかし、Ⅱでは、歌を受け取った人が、[B]が短歌の魅力だとすれば、AIが作った短歌に[C]と考えるようになった。
[A]~[C]にあてはまる内容を考えるために、まず見当をつけてから選択肢を見ていくようにしましょう。
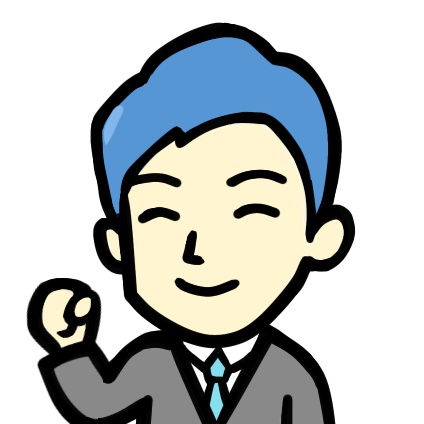
お子さんは[ ]に当てはまりそうな内容を答えられるでしょうか。ぜひ確認してみてください。
■[A]に当てはまる選択肢を導く
〈[A]に当てはまる内容の見当をつける〉
=線Ⅰ「こんなにグッときてしまう自分が、ちょっと怖かった」とあるので、「意図をもたないAIが作った短歌に感動した自分に動揺した」という内容があてはまると考えられます。
〈選択肢から正答を選ぶ〉
自分で考えた内容をもとに、選択肢を見ていきましょう。すると、正答は ア であると判断できます。
[正答] ア
→ 何の意思も持たないAIが作った歌を詠み、自分の心が揺さぶられてしまったことに動揺した。
=線Ⅰの「怖かった」という感情は、AIに感動させられることへの戸惑いや動揺を示しています。つまり「何の意思もない存在に心を揺さぶられた」という部分を言い換えたものがこの選択肢です。
■[B]に当てはまる選択肢を導く
〈[B]に当てはまる内容の見当をつける〉
[B]の前後を注意深く読むと、「歌を受け取った人が、[B]が短歌の魅力だとすれば」とあるので、短歌の魅力を答えれば良いことがわかります。「作者がAIでも、歌を自分なりに解釈できることも短歌の良さだ」と肯定的に捉えていると、見当をつけることができるのです。
〈選択肢から正答を選ぶ〉
自分で考えた内容をもとに選択肢を見ていくと、正答は ア であると判断できます。
[正答] ア
→ 心の内にとどめ、自分なりに理解をしたり、解釈を加えたりしながら、自分だけの歌に仕上げていく自由こそ
筆者は「AIが作者でも、歌としての価値が変わらない」と悟り、それは「読む人がどのように歌を受け止め、味わい直すか」という観点でした。短歌の魅力はむしろ読者がそうやって自ら解釈を加える自由さにあることを示しており、作者ではなく読み手の「受け取り方」に重点を置いた選択肢です。
■[C]に当てはまる選択肢を導く
〈[C]に当てはまる内容の見当をつける〉
=線Ⅱは筆者がAIの作る短歌を肯定的に捉えた内容です。[C]の前後に「AIが作った短歌に[C]と考えるようになった」とあるため、「AIが作った短歌に感動することも当然だ」という内容がふさわしいと見当をつけられます。
〈選択肢から正答を選ぶ〉
自分で考えた内容をもとに選択肢を見ていくと、正答は エ であると判断できます。
[正答] エ → 感動することは何もおかしなことではない
線Ⅱでは、筆者が「AI作者でも感動することに何の問題もない」と納得できたことが描かれています。この部分を的確に言い表しているのが「感動そのものはおかしくない」という内容の選択肢です。
(問7)選択問題 ー線⑦「一部の選考委員は批判的な発言をした」とありますが、この場合の「批判的な発言」とはどのようなものだと考えられますか。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「『批判的な発言』とはどのようなものだと考えられますか」という部分です。「批判的な発言」が具体的にどのような内容を指しているのか。つまり、「どんな点について批判されたのか」を本文から正しく読み取って考えることが求められています。
■本文から筆者の考えを読みとる
本文・82行目~「事実か事実でないかが作品の価値を決めるわけではないが、そこに『心』があるかどうかは大事なことではないかと思う」と書かれています。その脈絡から考えると、死をテーマに虚構で書くことに対して「嘘で人の感情を動かすのは良くない」と述べた発言が批判的な内容だと読み取れそうです。
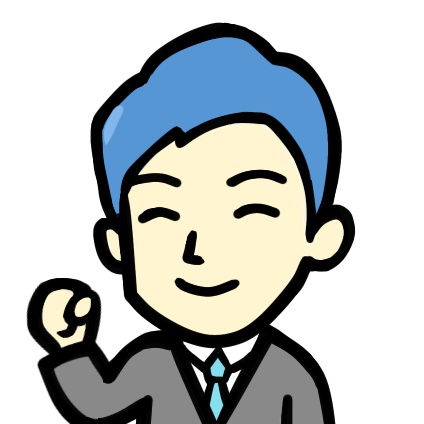
問題文で聞かれていることを正しく理解できているでしょうか。お子さんに「どんな批判があったんだと思う?」と尋ねてみましょう。
■選択肢の間違いを見つける
それぞれの選択肢を本文と照らし合わ、誤っているところを探していきましょう。
✕アの誤り
→ 「モラル」か「慣習」かを問題にしているが、本文では虚構そのものではなく「心の有無」が焦点。よってズレた内容です。
✕イの誤り
→ AIの短歌を歌ではないと言う否定的な立場ですが、選考委員の発言は「AI」ではなく、「虚構で感情を操作すること」への批判です。
✕ウの誤り
→ 歌は感情を揺さぶるものだとしながらも、その目的を「悪意による感情操作」と断じており、本文のニュアンス(心の向きに対する懸念)とは異なります。
つまり、「心」に対する懸念が書かれている エ の選択肢が正答であると判断できます。
[正答] エ
→ 人の死、特に身内の死は、誰もが心を大きく揺さぶられるデリケートなテーマだ。ただでさえ慎重な扱いが求められるのに、もし、それが嘘だということになれば、受け手は感情をもてあそばれたような不快感を味わうことになる。
(問9)記述問題 ー線⑧「恩返しをする鶴は、自分の羽を織りこむからこそ、輝く布を織ることができる」とありますが、これは木下さんが依頼者のリクエストに応えて短歌を詠む時の姿勢や作業の方針を表しています。木下さんはどのようなことに注意しながら、歌を詠んでいるのでしょうか。50字以内で、具体的に答えなさい。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「どのようなことに注意しながら」という部分です。―線部の比喩表現から、木下さんの創作姿勢や方針を具体的に答えることが求められている問題であるとおさえておきましょう。
■比喩表現を一般的な言い方に換える
―線⑧は、鶴の恩返しの比喩を用い、「自分の羽=自分自身の心・経験・感情」を短歌に織り込むことが大切である、と考えていることが読み取れます。
本文中では、木下さんが寄せられた依頼文に対して、以下のような発言をしています。
本文・103行目~「このテーマなら自分のこととして考えられそう」
本文・106行目~「自分の心の中のフックを探す」
本文・116行目~「依頼文を読んで、相手の気持ちに寄り添って短歌を創作するとき、そこに心の種は必要だ」
つまり、木下さんは依頼者の感情や背景を受け止め、自分自身の思いも込めて短歌を詠んでいるということが読み取れます。
■ポイントを整理して記述にまとめる
上記のポイントを整理すると、以下のようになります。
〈記述のポイント〉
・木下さんは自分自身の心を作品に反映させようとしている。
・自分自身の心だけでなく、依頼者の気持ちに寄り添うことも忘れていない。
これらのポイントを意識してまとめていきましょう。
[模範解答]
依頼文を読み、依頼者の気持ちに寄り添いながら、自分の心が感じたことを歌に込めるということ。
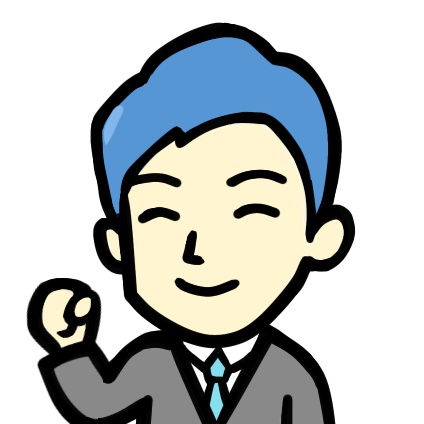
お子さんが比喩表現を読み取れていたか、確認してみてください。
四谷大塚「第2回合不合判定テスト」 随筆文まとめ
今回の随筆では、「AIが詠む短歌」という現代的なテーマを通して、短歌とは何か、表現に心は必要なのか、という本質的な問いが投げかけられていました。
俵万智さんは、AIの短歌に心を動かされた自分に戸惑いつつも、「読み手の心で完成する短歌の力」を認めます。そこからは、表現とは必ずしも作者の「心」があって初めて成立するものではなく、受け手の「心」がかかわることで真に意味を持つ、という新たな視点が提示されていました。
ご家庭でも、「誰がつくったか」より「どのように受け止めたか」について、お子さんと話し合ってみてください。
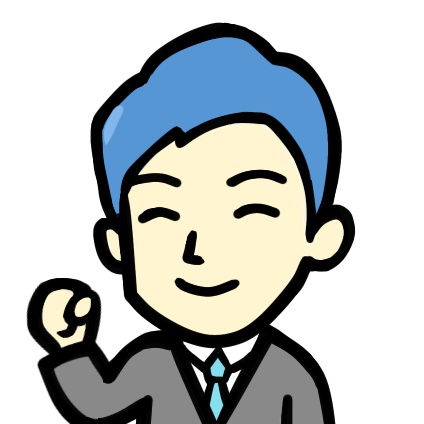
実際にAIに短歌を作らせて、その内容について意見を交わしてみるのもよいでしょう。今回の記事をぜひ参考にしてみてください。
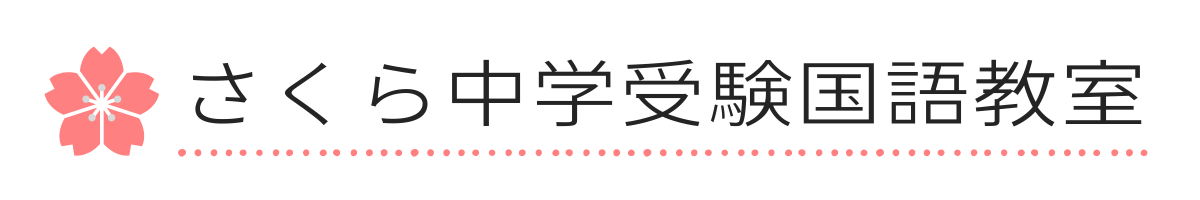



コメント