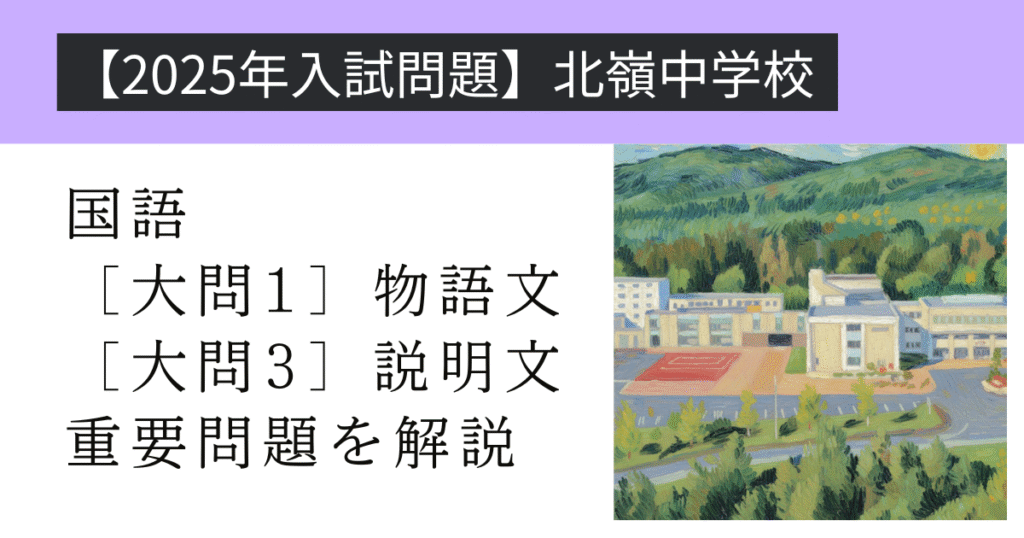
[大問1]物語文『夜光虫』(著:蓮見圭)
文章の概要
あらすじ
主人公の「ぼく」が祖父から、第二次世界大戦中に軍医長として潜水艦に乗っていた頃の話を聞く。潜水艦の生活は過酷で、乗組員は百人以上、病気や疲労とも闘いながら任務にあたっていた。
潜水艦は強力だが脆い兵器であり、戦局はすでに不利だった。そして、フィリピン沖の危険な海域で、夜光虫の光に敵艦の存在を察知し、いよいよ生死を分ける戦闘が始まる、という緊張感ある場面が語られる。
登場人物とその特徴
- 祖父(元軍医長):潜水艦に乗っていた経験を孫に語る人物。冷静で、戦争の過酷さや複雑さを淡々と伝える。
- 航海長:祖父の中学校の先輩。潜水艦の運用や戦術について詳しく、祖父に多くのことを教える頼れる人物。
- 艦長:最終的な判断を下す立場。輸送船への攻撃を見送るなど、慎重かつ的確な判断力を持つ。責任感の強いリーダー。
- 孫(語り手):祖父の話を聞く小学五年生の少年。祖父の体験を通して戦争や命の重さを感じ取っている。
難しい語句の解説
- 潜水艦(せんすいかん):水の中をしずんで進むことができる船。
- 魚雷(ぎょらい):水の中を進んで、敵の船に当たると爆発する武器。
- 浮上充電(ふじょうじゅうでん):潜水艦が海の上に出て、空気を入れ替えたり、電池を充電すること。
- プレッシャー:圧力、または精神的な重荷。
- 輸送船(ゆそうせん):ものや兵士を運ぶ船。戦闘用の船ではない。
- 航空母艦(こうくうぼかん):飛行機をたくさんのせることができる、大きな軍艦。
- 駆逐艦(くちくかん):潜水艦や飛行機を攻撃するための、スピードが速い軍艦。
- インドシナ海:ベトナムなどがある東南アジアの海。
- 夜光虫(やこうちゅう):海の中にいる小さな生き物で、夜になると青白く光る。
- 暗号長(あんごうちょう):暗号の通信を読み取る役目の人。
- 潜航配置(せんこうはいち):潜水艦がすぐに潜るための準備をすること。
- 聴音機(ちょうおんき):水の中の音を聞き取る機械。敵の船が近づいているのを知るために使う。
- 哨戒(しょうかい):敵がいないか見張ること。
- 圧搾空気(あっさくくうき):強い力で押しこめた空気。魚雷を発射するのに使う。
比喩表現と、比喩が表すもの
「潜水艦も人間と一緒だ。時々、休ませないと聞かなくなる。」
→ 潜水艦も機械でありながら、酷使すると調子を崩す、人間のように繊細な存在であることを示している。
「新鮮な空気は甘い」
→ 潜水艦内の息苦しさと、浮上して空気を入れ替えるときの生き返るような感覚を強調。
「運を天に任せるしかない」
→ 慣用句的な表現。潜水艦が敵に見つかったら、どうしようもない状況を表している。
物語の主題
戦争の極限状態における人間の選択と葛藤
→ 潜水艦という閉ざされた環境の中で、乗組員は生死をかけた判断を迫られる。輸送船を攻撃するか否かという判断に表れるように、戦争は単純な「敵を倒す正義」ではなく、命を守るための複雑な判断が必要であることが示されている。
戦争体験の語り継ぎ
→ 祖父の語りを通じ、孫が戦争の現実や人間の命の重さを学ぶ構造になっており、戦争の記憶を伝える意義が示唆されている。
重要問題解説 問4・問5
(問4)記述問題 ―②「敵の戦艦隊が近づいてきていることが分かった」とありますが、潜水艦はこの戦艦隊に、なぜ攻撃されなかったのですか。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「なぜ攻撃されなかったのですか」という部分です。「なぜ」と聞かれているので、攻撃されなかった理由を答える問題であることを確認しておきましょう。
この問題は15字以内で答える問題なので、問われていることに短く的確に答えることが求められます。
■本文を読んで答えを考える
―線部の前の記述を簡単に要約すると、以下のようになります。
潜水艦は敵を見つけたら攻撃するのが原則だが、輸送船を沈めるのは価値が低い。また、攻撃すると敵に見つかる危険もあるので、狙うのは航空母艦や戦艦など、重要な目標にすべきである。
このような極限状態の葛藤の中で、結局攻撃しない選択をしたのです。
つまり、攻撃されなかった理由は、「攻撃はリスクがあるため判断が難しく、攻撃せずに気づかれないよう待機していたから」ということになります。これを、15字以内にまとめましょう。
[正答] 存在を気づかれなかったから。
以下のような解答例も考えられます。参考になさってください。
[正答例] 敵を攻撃せずに隠れていたから。
(問5)記述問題 ―③「そんなこと」とは、どういうことですか。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「どういうことですか」という部分です。「どういうこと」と聞かれた問題は言い換える問題です。―線部の指示語を具体的に言い換えることが求められている問題だとおさえておきましょう。
■指示語の内容が書いてある場所を確認する
―線部の指示語を明らかにするため、―線部を含む一文と直前の文を注意深く読んでいきましょう。
この時、初めて夜光虫の話を聞いた。いや、耳にしたことくらいはあったが、実際にそんなことがあるのだと初めて知った。
「そんなこと」とは、直前の「夜光虫の話」であると分かりますが、具体的な内容はまだ書かれていません。
―線部の次の段落から、夜光虫の話の具体的内容が書かれています。
①夜光虫が船が出す白い泡に群がってくること
②海軍の捜索機が夜光虫の光に気づいて、敵が近くにいると判断したこと
②の内容が理解できたでしょうか。「敵はまだこちらに気づいていないようだが、単艦でない可能性が高い」という文から、夜光虫の光で敵の船の数を予想して、捜索機が連絡してきている様子を読み取ることができます。
■記述にまとめる
以上のことから、「そんなこと」が指す内容は、「海軍の捜索機が夜光虫の光に気づいて、敵が近くにいると判断したこと」であると読み取ることができます。
「夜光虫が船の泡に集まってくること」という解答では、語り手が伝えたいこととして不十分です。。
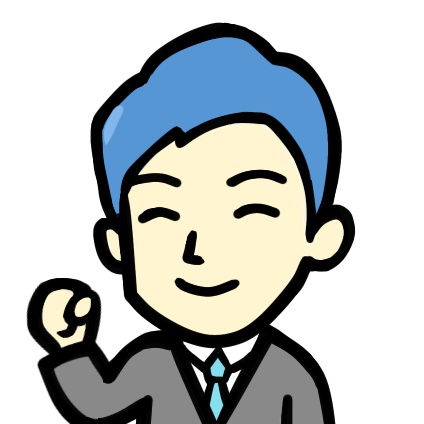
「夜光虫によって敵の船に気づき、戦闘の準備が開始された」という本文の流れに即した解答を心がけましょう。
[正答] 上空の飛行機が夜光虫の光によって敵の船の位置や数を察する、ということ。
[大問3]説明文『謝罪論』(著:古田徹也)
文章の概要
要約
謝罪には相手に赦しを求める意図が込められることが多い。だが、謝罪しても必ず赦されるわけではなく、まず謝罪が相手に受け入れられることが重要である。謝罪は被害者の損害回復や心の整理に役立ち、赦しへのきっかけにもなるが、赦しは外部から強制されるべきではなく、感情的な解放が伴ってはじめて成立する。感情としての赦しは意図的に作り出せず、被害者にも予期せず訪れるものである。
難しい語句の解説
- 履行(りこう):約束や義務を、実際に行って果たすこと。
- 受動的(じゅどうてき):自分から動かず、他の人や状況に合わせて動くこと。
- 契機(けいき):物事が始まるきっかけや原因となる出来事。
- 跡づけた(あとづけた):出来事や理由の順序・つながりをたどって、はっきりさせたこと。
- 社会的制裁(しゃかいてきせいさい):法律やルールだけでなく、世間の評判や非難によって受ける罰。
- 醸成(じょうせい):時間をかけて少しずつ作り出すこと。
- 次元(じげん):物事を考える立場や範囲、段階。
筆者の主張
- 謝罪は赦しを得るための重要な契機だが、それ自体が相手に受け入れられることが前提条件となる。
- 謝罪と償いは、被害者が損害や精神的混乱から回復する助けとなる。
- 赦しは周囲の圧力で強制されるべきではなく、被害者の感情の変化を伴ってはじめて本物になる。
- 感情としての赦しは意志ではコントロールできず、予期せず訪れる偶然の出来事(僥倖)である。
重要問題解説 問3・問4・問6
(問3)記述問題 ―①「自分の意志だけで常に実行できるわけではない」とありますが、筆者がそのように考えるのはなぜですか。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「筆者がそのように考えるのはなぜですか」という部分です。「なぜ、自分の意志だけで謝罪が実行できるわけではない」のか、本文から探していきましょう。
■「謝罪するために必要なもの」を読み取る
(本文)
普通、被害者から赦されることを望む加害者は、謝罪を実行しようとする。しかし、自分の意志だけで常に実行できるわけではない。相手に重大な損害が生じている出来事においては、相手に向かって自分勝手に「すみません!」と声をかけるだけでは謝罪にならない。それゆえ、たとえば相手と面会する時間を設けて、当該の出来事を自分がどのように受けとめているかや、いかに反省し、どう償おうとしているかを丁寧に伝えることが必要になるだろう。ことの重大さに応じて、謝り方というものは変わってくるのだ。
しかし、相手はそもそも会ってくれないかもしれない。ならば、同様のことを手紙に書いて送るのはどうか。しかし、相手はその謝罪文の受け取りを拒否するかもしれない。〈重い謝罪〉をするためには加害者は、謝罪によって被害者に赦される以前に、謝罪すること自体を許される必要がある。だからこそ、加害者はときに、手紙や電話などを用いて被害者にまずコンタクトをとって、 をさせてくださいと許可を求める必要が出てくるのである。
①ー線部の直後の文を読み取る
→「自分の意志だけで常に実行できるわけではない」という主張の直後に、なぜ自由にできないのかを具体的に説明する部分です。ここでは、ただ謝るだけでは不十分で、形式や内容が状況の重大さに応じて変わることが示されています。
②ー線部の次の段落を読み取る
直後の文では「謝り方の条件」を説明しましたが、次の段落ではさらに一歩踏み込んで、謝る機会そのものが相手によって拒否される可能性が述べられています。
つまり、加害者はまず「謝ること自体の許可」を得ないと謝罪が成立しない、という結論につながります。
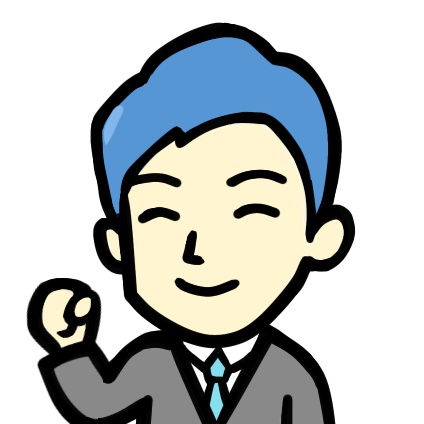
「しかし」などの対比表現や、「必要になる」などの筆者の考えが表れている文末に注目し、主張を読み取っていきましょう。
■読み取った内容をまとめる
今回、「自分の意志だけでできない理由」は、すぐ次の文で「ただ謝るだけでは不十分」と示され、その後の段落で「謝る機会すら許されない可能性」という補足が加わっています。
よって、解答を作るには①直後の文の主旨(ただ謝るだけでは不十分)+②次の段落の補足(謝罪の許可が必要)を組み合わせる必要があります。
この流れを踏まえると、設問の正答は以下のようになります。
[正答] 加害者は、相手に重い損害を与えた場合には、謝ること自体をまず許されなければならないから。
(問4)選択問題 ―②「多くの場合、その延長線上に『赦し』という契機が位置づくのである」とは、どういうことですか。
■(問われていること)を確認する
この問題で(問われていること)は「どういうこと」という部分です。「どういうこと」と問われているのは言い換える問題です。―線部の文を一般的な言い方に言い換えることが求められていることを押さえておきましょう。
■―②「その」の指示語が表すものを考える
ここでの「その」は直前の内容を指しています。本文で確認していきましょう。
(本文)
謝罪―および、その一環としての償いの約束と履行―は、被害者の物心両面の損害が修復され、受動的な混乱状態や無力感に苦しんでいる状態から回復し、状況に対する一定のコントロールを取り戻す、その手助けとなりうる。
つまり、この指示語は「謝罪や償いが、被害者の損害の回復や心の整理の助けになること」を指しています。
■―②「その延長線上に赦しという契機が位置付く」を言い換える
指示語の内容が確認できたので、―線部を言い換えてみましょう。
・「その」…謝罪や償いによって被害者が少しずつ回復していくと、
・「延長線上に赦しという契機が位置づく」…その流れの先に「赦し」という出来事が訪れることがある。 ※契機とは「きっかけ」という意味
つまり「謝罪がきっかけとなり、やがて赦しにつながる可能性が高い」ということ。
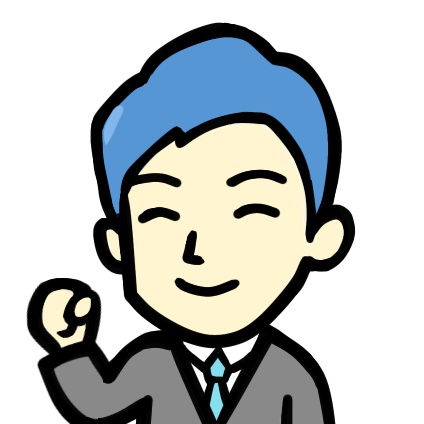
お子さんが言い換えられるか確認してみてください。
■選択肢の間違っている部分を見つけ正答を導く
選択肢は、間違っているところを見つける意識で読んでいきます。テストの振り返りでどこが間違っているかお子さんに説明させることで、読解力は高まります。
×イの誤り
→ 本文は「謝罪によって被害者との関係が元に戻る」とは述べていない。むしろ、元の関係に戻るのは難しいと最初に書かれている。
×ウの誤り
→「先に赦されること」が前提ではない。本文では「謝罪が許される」必要はあるが、それは謝罪の前段階であって、赦しそのものを先にもらうわけではない。
×エの誤り
→「必ず赦してもらえる」とは本文に書かれていない。むしろ、「謝っても赦されるとは限らない」と明記されている。
×オの誤り
→「感謝される」という内容は本文にない。また、謝罪の目的は感謝を得ることではなく、被害者の回復や区切りのきっかけになることと述べられている。
このように考えると、正答はアであると判断できます。
[正答] ア
→ 本文では「謝っても赦されるとは限らないが、大抵の場合、赦しに至るにはまず謝罪が必要」と説明しているため、これが②の趣旨に合致。
(問6)選択問題 ―線④「赦しの行為は決して予見できない」とありますが、この表現の、本文全体の内容をふまえた説明として最もふさわしいものを選びなさい。
■(問われていること)を確認する
この問題は「本文全体の内容をふまえた説明として最もふさわしいもの」を選ぶ問題です。「本文全体をふまえた」と書かれているため、本文の前半~後半部分の内容もふまえて考えることが重要です。
「赦しの行為が予見できない」理由を整理してみましょう。
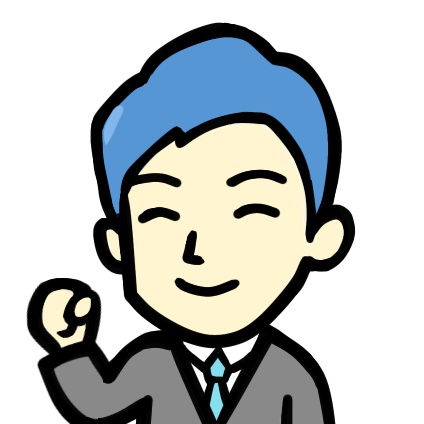
選択問題の答えを、まずは自分で考えられるかが重要です。問われていることと関係が深い文に線引きをさせるなどして確認しましょう。
■「赦しの行為が予見できない」ことと関連する記述を本文から見つける
本文では、次のような点が書かれています。
- 謝罪や償いは赦しのきっかけ(契機)になりうるが、謝罪したからといって必ず赦されるわけではない。
- 赦しとは、被害者が怒りや憎しみから解放されることを意味するが、それは自分の意志で赦そうと思っても、必ず赦せるわけではない。
- 感情は自分の思い通りにはならず、赦しの感情も「いつの間にか訪れる」もので、被害者自身にも予測できない。
これらを整理すると、 謝罪があってもなくても、赦しの感情がどのタイミングで生まれるかは、被害者自身も知ることはできないということになります。
■選択肢の間違っている部分を見つけ正答を導く
まずは、選択肢の間違っている部分を見つけていきましょう。
×アの誤り
→加害者が手順をふんで謝ることが求められるが、それは「加害者にとって重要な区切りにする」ためではなく、被害者に赦しを乞うために必要なことなので間違い。
×イの誤り
→本文は「条件を満たせば赦される」とは言っていない。損害回復や償いは契機にはなるが、赦されるかどうかは感情で決まるため、条件充足=赦し ではない。
×ウの誤り
→「謝罪の時期」については本文に触れられていない。本文の主張は「謝罪しても必ず赦されるわけではなく、赦しの感情は予測不能」という点にある。
×オの誤り
→本文は「正しく謝れば必ず赦される」とは述べていない。むしろ「謝罪はきっかけにすぎず、赦されるかは分からない」としている。
「赦しの感情がどのタイミングで生まれるかは不明確である」という内容であるエが正答であると判断できます。
[正答] エ
加害者は申し訳ないという思いを相手の事情もふまえて伝える必要がある。一方、謝ったとしても被害者がそれをどう感じるかは不確かで、その時になってみなければ赦されるかどうかは分からない。
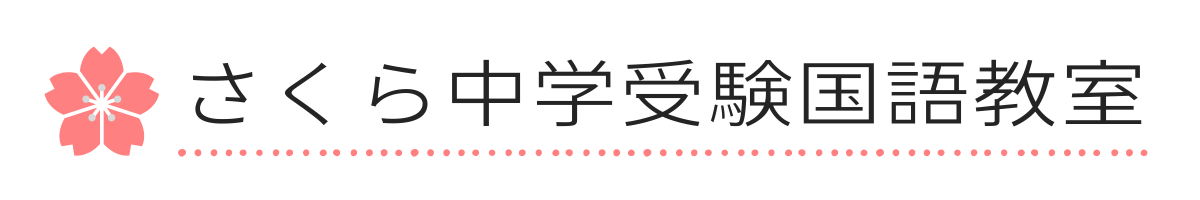
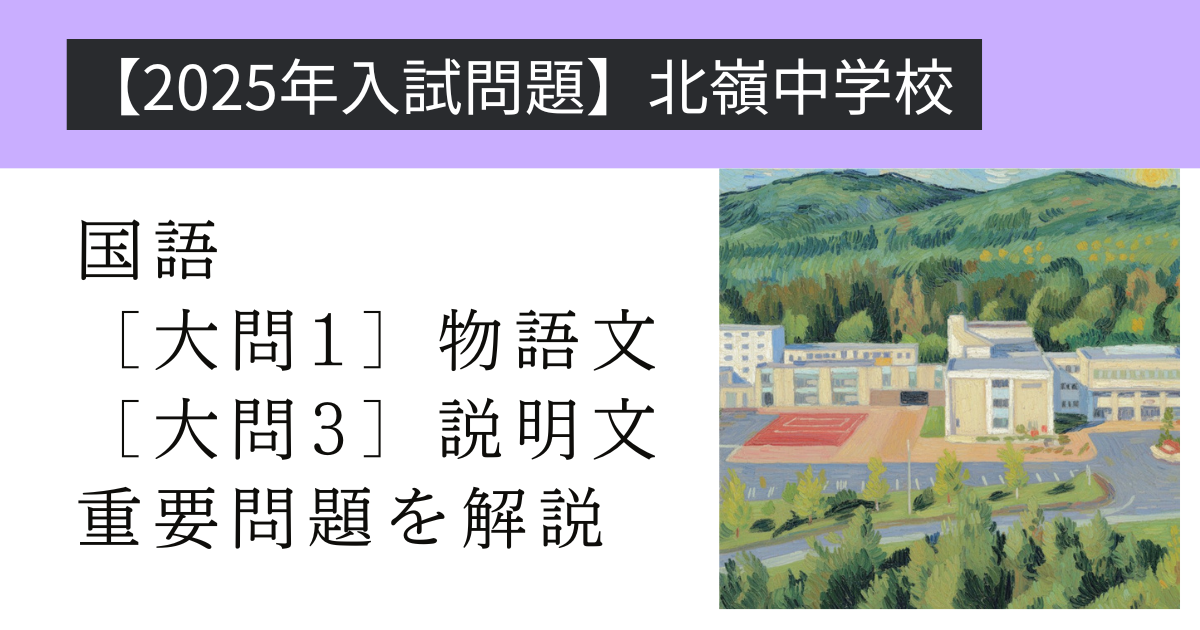

コメント